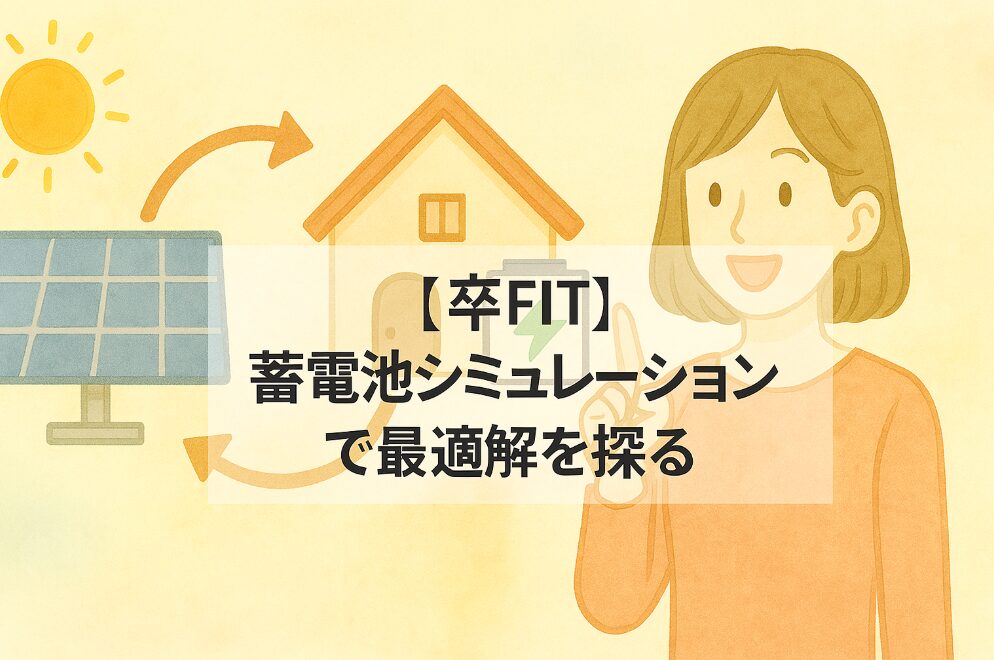❕本ページはPRが含まれております
卒FIT 蓄電池シミュレーションを検索している方は、売電単価が下がった後に何を基準に判断すべきか、最適な容量や回収年数がどのくらいになるのか、そして時間帯別料金をどう活かせば家計が改善するのかを知りたいはずです。
資源エネルギー庁は卒FITの基礎と選択肢を「どうする?ソーラー」で整理し、時間帯別料金の考え方も公表しています。
本記事では、条件設定の透明性を重視し、前提値と計算ロジックを明示しながら、売電継続と自家消費、さらには夜間充電を含む複数の運用シナリオを比較します。家庭の需要プロファイルや蓄電池の劣化を踏まえ、数字で納得できる判断材料を提供します。
この記事でわかること
- 卒FIT後に有効な運用シナリオの見極め方
- 蓄電池容量と実効容量の設計手順
- 回収年数やNPVなど経済性評価の読み方
- 時間帯別料金と市場連動売電の扱い方
卒FIT 蓄電池シミュレーションで分かる最適な選択肢

卒FIT後の売電単価と買電単価の関係
卒FITを迎えると、売電単価は一般に7〜9円/kWh程度まで低下する一方、買電単価は昼間が高く夜間が比較的安い傾向があります。差が大きいほど、余剰電力を売るよりも家庭内で使う価値が高まりやすくなります。
判断の軸は、日中の買電回避による削減額と、余剰売電で得られる収入のどちらが大きいかです。家庭の需要が夕方〜夜に偏る場合、蓄電池で昼間の発電を貯めて夜に使うと差額効果が積み上がります。
夜間単価が十分に低いプランであれば、夜間に充電して昼間に放電する運用も選択肢になります。以上の点を踏まえると、単価差と需要パターンを合わせて見ることが合理的な出発点になります。
自家消費率と自給率の違いを理解する
自家消費率は発電量のうち自宅で使った割合、自給率は総消費量のうち自家発電で賄えた割合です。前者は売電に回さず使えた比率、後者は電力会社からの購入依存度の低さを示します。
蓄電池の導入で自家消費率は上がりやすく、同時に自給率も改善します。ただし、往復効率や出力制約によって実際に使えるエネルギーは減少します。
したがって、指標の改善幅は蓄電池の仕様と運用方針に左右されます。自家消費率と自給率を併記し、時間別の内訳まで確認すると、運用の改善余地が把握しやすくなります。
蓄電池の容量設計と実効容量の考え方
容量設計は定格容量そのものではなく、実効容量で考えることが肝要です。実効容量は定格容量にDoD(深放電深度)と往復効率を掛け合わせた値で、実運用で取り出せる目安になります。
夕方〜夜の需要量、さらにPCS(パワーコンディショナ)の出力制約を踏まえてサイズを見積もります。過大にするとSOCが高止まりしてサイクル数が伸びず、回収が遅れがちです。逆に小さすぎるとピークを賄えず、買電が残ります。
以上の点から、需要ピークをカバーしつつ過大にならない控えめの実効容量が経済合理性につながります。
実効容量の簡易式
実効容量=定格容量×DoD×往復効率
例:10kWh×0.9×0.9=約8.1kWh(目安)
TOU(時間帯別料金)を活かした運用シナリオ
TOUでは夜間が割安、昼間が割高になることが一般的です。昼間の買電回避メリットが夜間の充電コストを上回る場合、夜間充電→昼間放電で家計改善が見込めます。
一方で、日中に太陽光が十分に余る家庭では、まずは発電余剰を優先的に充電し、残りを売電する自家消費最大化の運用が適します。
停電時に備えて予備SOCを下限として確保する設定を行うと、経済メリットはやや低下しますが、レジリエンスが高まります。これらのことから、TOU活用は自家消費と夜間充電のバランス設計が鍵となります。
卒FIT買取単価の比較と選び方
卒FITの買取は固定単価型、キャンペーン型、市場連動型などバリエーションがあります。固定は収支が読みやすく、キャンペーンは条件次第で高単価が期待できますが期間や定員の留意が必要です。市場連動は平均が高い時期には有利でも、変動により下振れの可能性があります。
比較の際は、前提となる手数料や受給条件、セット割の縛り、契約期間などの条項を確認し、TOUプランとの相性も含めて総合評価することが望まれます。
卒FIT 蓄電池 シミュレーションで見る経済性と回収年数

蓄電池の劣化率とシミュレーション精度
蓄電池は年3〜4%程度の劣化を想定すると、実効容量と往復効率が年次で逓減します。シミュレーションでは、容量・効率・発電量の劣化を反映し、年次キャッシュフローを時系列で評価します。
また、充放電回数や放電深度の運用方針で劣化が変わり、保証条件にも影響します。
過度な深放電を避け、必要十分な放電幅に抑えることで、経済性と寿命のバランスがとりやすくなります。以上の点を踏まえると、回収年数は固定値ではなくレンジで示し、感度分析で幅を確認する姿勢が現実的です。
感度分析の例
-
単価変動:買電・売電を±3円/kWhで再計算
-
劣化率:±1%/年で再計算
-
実効容量:±10%で再計算
補助金制度と初期費用の影響を整理する
初期費用は本体価格だけでなく、工事費、申請費、点検費、将来のPCS更新などをLCC(ライフサイクルコスト)に含めて評価します。自治体や国の補助金がある場合、自己負担が圧縮され、回収年数が短くなる傾向があります。
ただし、交付要件や申請期限、対象機器の条件などの実務面を満たす必要があります。補助がなかった場合の回収年数も並行して確認し、制度変更の影響を受けても意思決定が揺らがないかを点検すると、投資判断の確度が高まります。
市場連動型売電プランのメリットとリスク
市場連動は価格が高い時期には収入が伸びやすい一方、価格低迷期には想定より収入が減る可能性があります。過去の平均値だけでなく、変動幅や分散を踏まえた評価が欠かせません。
蓄電池を併用する場合、価格の高い時間帯に放電し、低い時間帯に充電する戦略が理論上は有効です。
ただし、往復効率や容量制約、需要のタイミングとの整合を取る必要があり、必ずしも理想どおりにはいきません。以上の点から、固定と連動の両シナリオを走らせ、収支の上下を比較することが実務的です。
停電対策と非常用電源としての活用ポイント
非常用負荷に電力を供給する設計にすると、平時の経済性は数%ほど低下しがちですが、停電への備えという価値を同時に得られます。
予備SOCを下限として維持し、重要負荷の稼働時間を確保する方針を明記すると、運用が安定します。PCSの切替方式や自立運転時の出力上限、同時使用家電の優先順位など、実際の生活に合わせた設定を検討すると、想定外の停止を避けやすくなります。
シミュレーション結果の読み方とKPI指標
結果の提示では、前提単価(買電・売電・基本料金等)と、蓄電池・PVの劣化、PCS更新、点検費を含むLCCを明示します。
KPIとして、自家消費率、自給率、年間キャッシュフロー、累積キャッシュフロー、回収年数、NPV、IRR、充放電回数、損失(往復効率)を示すと、投資効果を多面的に確認できます。
さらに、3本柱のシナリオ(売電継続、自家消費最大化、TOU最適運用)を横並びで比較すると、家庭の需要プロファイルに対する適合度が見えてきます。
代表シナリオの比較表(例)
| 指標 | 売電継続 | 自家消費最大化 | TOU最適運用 |
|---|---|---|---|
| 自家消費率 | 低 | 中〜高 | 中〜高 |
| 夜間充電活用 | なし | 限定的 | 積極的 |
| 収支の安定性 | 高 | 中 | 中 |
| 単価差の影響 | 中 | 高 | 高 |
| 停電備え適合 | 中 | 高 | 高 |
卒FIT 蓄電池シミュレーションまとめ
まとめ
- 単価差と需要プロファイルを起点に最適運用を選ぶ
- 実効容量とPCS出力を基準に過不足ない容量を決める
- 劣化と効率低下を年次で反映し回収年数はレンジで把握する
- 固定売電と市場連動を併走し変動リスクへの耐性を確認する
- TOUの夜間単価と昼間単価の差を活かして運用を最適化する
- 非常用負荷の確保は経済性の微減と引き換えに安心を得られる
- LCCに工事費申請費点検費PCS更新を含め総額で判断する
- KPIは自家消費率自給率回収年数NPVIRRを揃えて確認する
- 需要ピークの時間帯と放電出力の整合を最初にチェックする
- キャンペーン買取は条件期間定員を把握し恒久前提にしない
- 夜間充電は往復効率と損失を踏まえ採算ラインを明確にする
- 発電余剰の季節差を見込み時間別にロジックを調整する
- 補助金は要件と締切を確認し不採択時の回収年数も把握する
- 年次の劣化や単価変動を感度分析で見える化して意思決定する
- 家庭の生活パターンに合わせた運用ルールで効果を継続させる
参考サイト
-
資源エネルギー庁|どうする?ソーラー(卒FITの基礎・選択肢) — 買取期間10年後の対応と売電以外の選択肢を整理。 エネルギー・環境政策ポータル
-
資源エネルギー庁|特集記事「FIT満了、その後どうする?」 — 卒FITの考え方を平易に解説。 エネルギー・環境政策ポータル
-
資源エネルギー庁|料金制度(時間帯別料金の説明) — TOUの基本とプラン設計の考え方。 エネルギー・環境政策ポータル
-
資源エネルギー庁|時間帯別料金メニューの取扱い(FAQ) — 計量と表示など運用上の留意点。 エネルギー・環境政策ポータル
-
NEDO 報告書(定置用蓄電池の性能・劣化評価の知見) — サイクル劣化等の技術的前提を確認。 NEDO+1
-
学術論文|家庭用PV+蓄電の経済性評価(J-STAGE) — 電力データを用いた評価手法の参考。 J-STAGE
-
TEPCOグループ(EV活用/自家消費の実務解説) — 卒FIT後は自家消費優位となる傾向の事例紹介。 EV DAYS | 東京電力エナジーパートナー