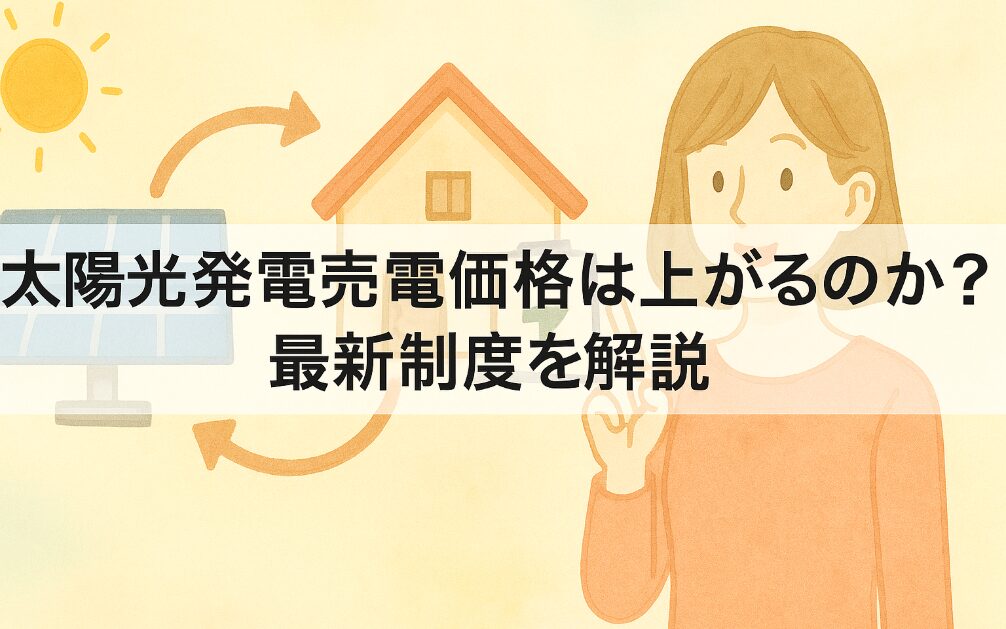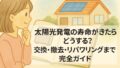❕本ページはPRが含まれております
太陽光発電 売電価格 上がるのかを知りたい方に向けて、2025年度の制度改定で何が起きるのか、上期と下期で何が変わるのか、そして家庭や事業の意思決定にどう影響するのかをわかりやすく整理します。
初期だけ単価が上がる新しい設計や、のちに下がる単価とのバランス、自家消費や蓄電池の考え方まで、実務の流れに沿って丁寧に説明します。制度の背景・詳細はエネ庁の価格表および経済産業省の発表をご確認ください。
本記事では、「初期だけ単価が上がる設計」とのちの低単価期をどう噛み合わせるか、上期・下期どちらで認定を取ると長期収益がどう変わるか、自家消費や蓄電池の戦略まで、実務フローに沿ってわかりやすく解説します。
太陽光発電の全体像を整理したい場合は、
▶ 太陽光発電と蓄電池の完全ガイド
を参考にしてください。
この記事でわかること
- 2025年度の制度変更と単価の全体像を理解できる
- 上期と下期で変わる売電単価の違いを把握できる
- 住宅や屋根設置での収益設計の考え方が分かる
- 認定時期や費用項目への注意点を確認できる
太陽光発電売電価格は上がるのか? 最新動向

2025年度の制度変更要点
2025年度は、同じ年度の中でも上期と下期で売電単価の考え方が分かれます。大きなポイントは、住宅と事業用の屋根設置を対象に、初期の数年間だけ高い単価を適用し、その後は低い単価に段階的に移行する仕組みが導入されたことです。
初期投資の回収を前倒しし、屋根上の設置を後押しする狙いが背景にあります。一方で、地上設置や入札対象の区分では、従来の水準や入札結果に沿った設定が続くため、すべての区分で単価が上がるわけではありません。
上期と下期で単価が違う
2025年度は4月から9月までの上期と、10月から翌年3月までの下期で、同じ区分でも単価が異なります。上期は従来のフラットな単価設定、下期は初期年だけ高く、その後に低くなる段階型です。
この違いは、認定のタイミングで固定されるため、申請スケジュールや工事計画の管理が実務上の鍵となります。どの月に認定を取得するかで、10年間(住宅)や20年間(事業)の収益構造が変わるため、年度内でも時間軸を意識した意思決定が求められます。
住宅は24円その後8.3円
住宅用の単価は、下期の認定から初期4年間が24円、その後の6年間は8.3円となります。家計の視点では、昼間の買電単価が24円を上回ることが多いため、売るよりも自家消費で買電を減らすほうが利得になる場面があります。
したがって、最初の4年間は売電収入で初期費用の回収を進めつつ、同時に自家消費率を設計的に高めておくと、5年目以降の単価低下局面でも家計メリットを維持しやすくなります。
年度別の住宅用比較(認定月別)
| 認定時期 | 単価・年数 | 備考 |
|---|---|---|
| 2025年4〜9月 | 15円×10年 | 従来型のフラット |
| 2025年10月〜 | 24円×4年 → 8.3円×6年 | 初期投資回収の前倒し設計 |
屋根設置は19円から8.3円
事業用の屋根設置(10〜50kW未満)は、下期認定から最初の5年間が19円、6年目以降は8.3円が適用されます。工場や倉庫など需要家の屋根では、昼間の使用電力と売電を組み合わせて回収する設計が現実的です。
5年目までの高単価期間に設備費の大部分を回収し、6年目以降は自家消費比率の引き上げやPPAの組み合わせでキャッシュフローの安定化を図ると、長期の発電収入が滑らかになります。
年度別の屋根設置比較(認定月別)
| 認定時期 | 単価・年数 | 備考 |
|---|---|---|
| 2025年4〜9月 | 12円×20年 | 従来型のフラット |
| 2025年10月〜 | 19円×5年 → 8.3円×15年 | 初期年強化の段階型 |
地上設置と入札は据え置き
10〜50kW未満の地上設置は、上期で11.5円が示され、下期も段階型の対象外です。50kW以上の区分は入札により上下しますが、足元は1桁円台後半での推移が目安になります。
大規模側はコスト反映や競争環境が強く、単価の上振れを期待するよりも、設備費や造成コストの最適化、並びに系統連系や工期管理で総事業費を抑える視点が現実的です。
太陽光発電売電価格上がる時期と対策

FITとFIPの違いを整理
FITは、認定時の単価が住宅で10年、事業で20年固定される制度です。2025年度下期から一部区分で初期年だけ高い単価にする段階型が導入され、収益の前半寄りが強化されました。
FIPは市場価格にプレミアムを加える方式で、卸電力市場の価格に連動します。FITは価格確定で銀行調達に乗せやすい一方、FIPは価格変動を取り込みやすく、需給が締まる時期は上振れ、低迷時は下振れが起こります。
どちらを選ぶかは、自家消費の有無、資金調達の方針、価格変動の許容度で判断すると整合的です。
JEPX価格の影響と指標
市場連動のFIPや卒FIT後の買取は、JEPXのスポット価格に左右されます。年平均ベースでは上下を繰り返しており、気温要因や燃料価格、需給ひっ迫の警報発令時などに短期的な高騰が見られることがあります。
計画上は、平常時の想定価格とピーク時の上振れ、そして底値局面の下振れを区別して見積もると、収益シナリオが安定します。相対契約やアグリゲーションを組み合わせると、変動リスクの平準化が狙えます。
認定タイミングの注意点
単価は認定月に紐づくため、申請から運転開始までの工程を逆算したスケジュール設計が欠かせません。上期と下期で制度が切り替わる年度は、認定取得の月がその後10年または20年の収益に影響します。
需要家の決算期や工事の混雑期、系統連系の審査期間を踏まえて、工期や資材の確保を前倒しすると、望む単価テーブルに乗せやすくなります。特に屋根設置は建屋の耐荷重調査や防水施工の調整が必要で、工程の遅延が認定の取り逃しに直結しかねません。
発電側課金と消費税の扱い
10kW以上の案件では、発電側課金の上乗せの考え方が示されており、見積や事業計画に反映させる必要があります。さらに、消費税の課税事業者か免税事業者かで、売電収入や設備費の取り扱いが変わる点にも留意します。
これらの費用項目は、単価だけを見ていては見落としやすく、キャッシュフローの差異となって現れます。設計段階で費用の科目別にシートを用意し、単価テーブルと合わせて感度分析を行うと判断がしやすくなります。
チェックリスト例(費用・手続き)
| 項目 | 内容の要点 |
|---|---|
| 発電側課金 | 10kW以上は相当額の上乗せを確認 |
| 消費税区分 | 課税/免税の判定と申告方針を確認 |
| 認定月管理 | 上期/下期のどちらで固定されるか |
| 工程計画 | 調達、施工、連系の順で遅延対策 |
自家消費と蓄電池の戦略
初期年の高単価は魅力ですが、住宅で5年目以降、屋根設置で6年目以降は8.3円に下がるため、長期では自家消費の比率が実質的な収益を左右します。家庭ではHEMSや高効率家電の導入、事業では負荷平準化や設備の稼働時間調整で、自家消費率を段階的に高める設計が有効です。
蓄電池はピークカットと余剰の時間移動を同時に実現でき、買電単価と売電単価の逆転局面で効きます。配電容量や契約電力の見直しと併せて検討すると、投資対効果が見極めやすくなります。
太陽光発電売電価格まとめ
太陽光発電の全体像を整理したい場合は、
▶ 太陽光発電と蓄電池の完全ガイド
を参考にしてください。
まとめ
- 2025年度は住宅と屋根設置で初期年のみ増額
- 上期はフラット単価で下期は段階型が適用
- 住宅は24円の後に8.3円へ段階的に移行
- 屋根設置は19円の後に8.3円で長期運用
- 地上設置や入札は従来水準で推移
- 認定月が長期収益を決める重要な基準
- 市場連動はJEPXで上下し想定が必要
- 初期回収は売電と自家消費の両輪で設計
- 蓄電池はピークカットと時間移動で有効
- 発電側課金と消費税の区分を事前に整理
- 工程管理と資材調達で認定タイミング確保
- 需要家屋根はオンサイト最適化が鍵
- 地上設置はコスト最適化と入札動向を注視
- 家庭は買電単価との比較で自家消費を強化
- 長期は自家消費率の高止まりが安定化につながる
参考サイト
-
資源エネルギー庁|買取価格・期間等(2025年度以降の価格表)
2025年度の上期/下期の価格(住宅:24円→8.3円、屋根設置:19円→8.3円 等)を一次情報で確認。 エネーチョウ -
経済産業省プレスリリース(2025年3月21日)
入札対象や2025年度の入札上限価格(8.90/8.83/8.75/8.68円)など制度全体の位置づけ。 経済産業省 -
FIT・FIP制度ガイドブック(2025年度版・PDF)
段階型(初期増額→後年低単価)スキームの整理や制度運用の要点。 エネーチョウ -
過去の買取価格・期間(2012–2024年度)
価格決定ルールと過年度推移の確認用。 エネーチョウ -
調達価格等に関する資料(PDF・国会提出資料)
2025年度の入札上限価格のイメージ等の補足。 衆議院