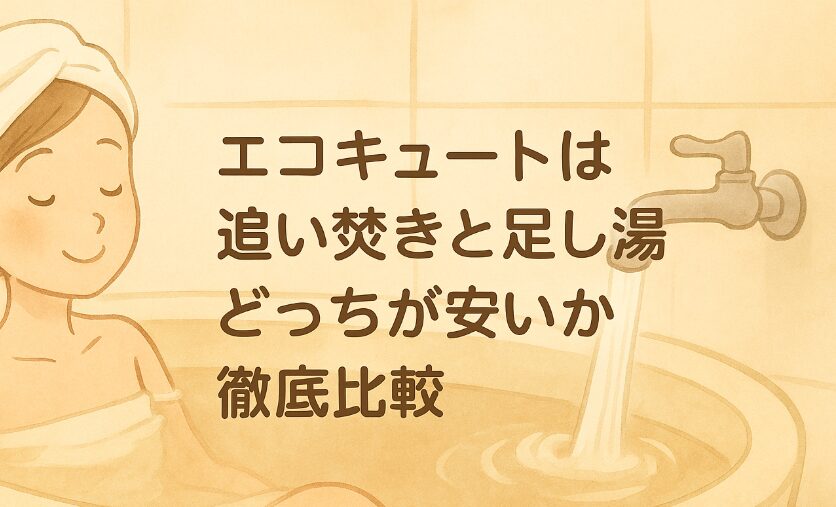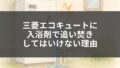❕本ページはPRが含まれております
エコキュート 追い焚き 足し湯 どっちが安いという疑問は、多くの家庭で毎日の光熱費に直結する関心事です。
この記事では、仕組みからコストの考え方、使い分けのポイントまでを体系的に整理し、迷いを解消できるようにわかりやすく解説します。初期設定や日々の運用で変わる費用の差を、具体例とともに丁寧に示します。
この記事でわかること
- 高温足し湯と追い焚きの仕組みの違い
- 世帯別に最適な使い方と注意点
- 季節や時間帯で変わるコストの考え方
- 失敗しない設定と節約テクニック
エコキュートは追い焚きと足し湯どっちが安い?基本の仕組み

エコキュートの仕組みと節約原理
エコキュートはヒートポンプで空気の熱を集め、少ない電力で貯湯タンクにお湯を作ります。深夜などの安い電力時間帯に効率よく湯を貯められるため、同じ湯量でも電気ヒーター方式より電気使用量を抑えられるのが強みです。
貯湯タンクからは給湯や高温足し湯で熱を取り出し、浴槽の温度維持やシャワーに活用します。節約の基本は、この貯湯量と使用量のバランス管理です。
余裕をもって貯めすぎると翌日の残湯が増えてロスが生じ、逆に不足すると高温足し湯や追加沸き上げの頻度が増えてコストがかさみます。したがって、家族の入浴時間帯や使用パターンに合わせた湯量設定が鍵となります。
追い焚き機能の特徴と電気代の仕組み
追い焚きは浴槽の水を循環させ、熱交換器で間接的に温め直す仕組みです。浴槽の水を入れ替えずに温度を上げられるため、水道の追加使用は抑えられますが、熱交換器を動かすための電力が必要です。
一度の追い焚き時間が長い、あるいは短時間に繰り返すと、合計の電力使用量が増えます。また、遅い時間帯に何度も追い焚きすると、翌日の沸き上げに影響し、トータルの電気代が高くなる場合があります。
入浴の間隔が短い家庭では一定の利点がありますが、長時間の保温や再加熱を前提とする運用は割高になりやすいと考えられます。
高温足し湯の特徴とメリット・デメリット
高温足し湯は、貯湯タンクの高温のお湯をそのまま浴槽に供給し、浴槽の温度と湯量を同時に上げる方式です。熱交換器を動かさないため、加熱のための追加電力をほとんど使わず、短時間で温度を持ち上げられます。
一方で、タンク内の貯湯を直接消費するため、繰り返し行うと残湯量が減り、お湯切れのリスクが高まります。特に複数人が連続して入浴する家庭や、冷えた浴槽を一気に温めたいケースでは、タンク残量の管理が欠かせません。
目的は達成しやすいものの、残量を見ずに多用すると、結果的に翌日の追加沸き上げが必要になり、計画外のコスト増につながる可能性があります。
高温足し湯が安いと言われる理由を分析
高温足し湯は熱交換器の稼働を伴わないため、瞬間的な電力消費が小さく、目的温度まで素早く近づけられます。特に短時間で数度上げたいときや、入浴直前に温度を整える用途では効率的です。
以下は、両方式の特徴を整理した比較表です。
| 比較項目 | 高温足し湯 | 追い焚き |
|---|---|---|
| 主なエネルギー消費 | 既存貯湯の放出 | 熱交換器駆動の電力 |
| 温度上昇の速さ | 速い | やや遅い |
| 水量変化 | 増える | 変わらない |
| 繰り返し使用の影響 | タンク残量を消費 | 電力消費が蓄積 |
| 想定される弱点 | お湯切れの懸念 | 長時間運転で割高化 |
以上の点を踏まえると、単発の温度調整では高温足し湯が有利と言えます。ただし、タンク残量を削ってまで何度も実行すると、翌日の沸き上げ負担が増えるため、総合コストは使い方次第で逆転し得ます。
お湯切れのリスクと注意すべきポイント
お湯切れは入浴計画の破綻だけでなく、衛生面や快適性の低下にも直結します。高温足し湯は貯湯を直接使うため、以下の観点での管理が必要です。
タンク残量の把握
入浴前後での残量チェックを習慣化します。家族の入浴順や浴槽の容量、追い焚きの要否を見通す材料になります。
追加沸き上げのタイミング
深夜の安価な時間帯に翌日の使用量に合わせて沸き上げ設定を調整します。計画外の昼間の追加沸き上げは、料金単価が高い場合があり不利になりがちです。
使い分けのルール化
浴槽温度が数度下がっただけなら高温足し湯、長時間放置して大きく冷めた場合は追い焚き、というように家庭内の基準を決めておくと無駄が減ります。
これらのことから、残量と時間帯を意識した運用が、快適さとコストの両立に直結します。
エコキュートは追い焚きと足し湯どっちが安い?最適な使い方

最適な使い方
家族構成別のおすすめの使い方
世帯人数や入浴の間隔によって最適解は変わります。少人数世帯では、入浴間隔が短く、浴槽が大きく冷めにくい傾向があります。こうした場合は、高温足し湯で素早く温度を整える運用が負担少なく機能します。
一方、大家族で入浴時間がばらつく家庭では、浴槽が冷めやすく、温度調整の頻度が増えがちです。熱交換器を用いる追い焚きで水量を増やさず温度を維持する選択が安定しやすい場面があります。
実運用のヒント
・連続入浴が続く日は高温足し湯を中心に組み立てる
・入浴が夜遅くに分散する日は追い焚きの利用比率を高める
・週末など使用量が多い日は、前夜の貯湯量を1段階増やす
光熱費を抑えるための時間帯設定のコツ
電力単価が安い時間帯に沸き上げを集中させることが基本です。深夜電力プランを利用している場合、翌日の使用量を見越して沸き上げ量を設定し、日中の追加沸き上げを極力避けます。
また、夜間の追い焚きを何度も行うと、その日のトータル消費が膨らみがちです。入浴時刻をそろえる、保温蓋を活用するなど、温度低下を防ぐ工夫が節約に直結します。
家庭内のスケジュールを共有し、曜日ごとに「高温足し湯中心の日」「追い焚き中心の日」を決めておくと、無駄な再加熱が減りやすくなります。
節約になるエコキュートの設定温度とは
設定温度は高すぎると貯湯時のエネルギーが増え、低すぎると入浴時に高温足し湯の頻度が増えます。一般的には、季節や家族の好みに合わせつつ、必要最小限で安定する温度帯を探るのが現実的です。
見直しの手順
1週間単位で「設定温度」「高温足し湯回数」「追い焚き時間」をメモし、快適さを損なわない範囲で1〜2度ずつ調整します。結果として高温足し湯の回数が減る、あるいは追い焚き時間が短くなる温度に落ち着けば、トータルコストは下がりやすくなります。
要するに、固定観念ではなく、実データに基づく微調整が無駄を削る近道です。
冬場と夏場での使い分けポイント
冬は浴室や浴槽の放熱が大きく、追い焚きの出番が増えます。保温蓋の使用、入浴間隔を短くする、浴室暖房で室温を底上げするなど、冷めにくい環境づくりが効果的です。
夏は放熱が小さいため、高温足し湯で素早く温度を整える運用が効率的に働きます。貯湯量もやや控えめでも成立しやすく、沸き上げの電力を圧縮できます。
以上の点を踏まえると、季節で「基準の使い方」を入れ替え、細部を調整する柔軟性が費用を左右します。
お湯を無駄にしない日常の工夫
浴槽の容量に対して実際に必要な水位を見直し、適量で運用するだけでも、余計な高温足し湯や追い焚きの頻度が減ります。入浴後はすぐに保温蓋を閉める、シャワーの予熱時間を短縮する、洗濯の温水利用と入浴タイミングを合わせるなど、細かな工夫の積み重ねが効きます。
また、家族で入浴順を決めて間隔を詰めるだけで、温度低下を抑えられます。これらの実践により、どちらの方式を選んだ場合でも総合コストを下げやすくなります。
まとめ:エコキュート追い焚きと足し湯
まとめ
・短時間の温度調整は高温足し湯が有利になりやすい
・長時間の保温や再加熱は追い焚きの出番が増えやすい
・家族の入浴間隔が短い日は高温足し湯中心が向く
・入浴が分散する日は追い焚きの方が安定しやすい
・貯湯タンクの残量管理がコスト最適化の前提となる
・深夜の安価な時間帯に沸き上げを集中させておく
・設定温度は実測データで段階的に最適化していく
・保温蓋や入浴順の工夫で温度低下を抑制しておく
・冬は放熱が大きく追い焚き時間の管理が必要になる
・夏は放熱が小さく高温足し湯の相性が良くなる
・水位の適量運用で無駄な追加加熱の発生を抑える
・計画外の昼間の追加沸き上げは避けるようにする
・週末など使用量が多い日は前夜の貯湯量を増やす
・方式の固定化より状況に応じた使い分けが効果的
・最終的な安さは家庭の習慣と時間帯設定で決まる